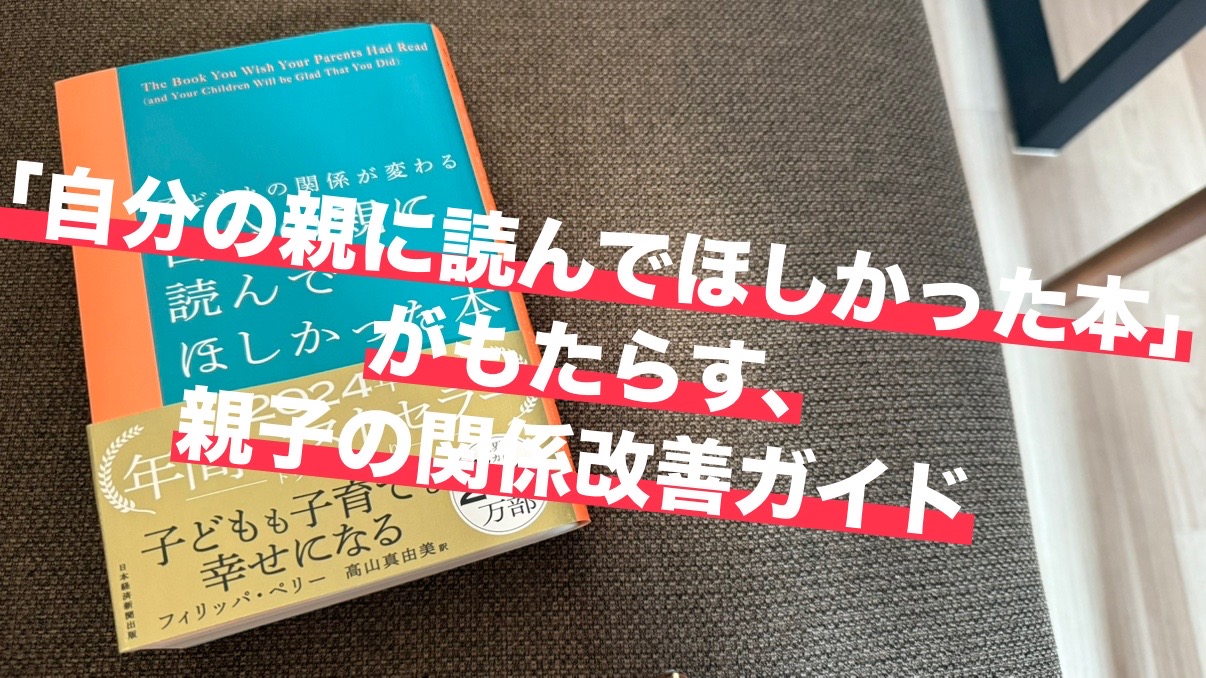
次の方向けの記事です。
🍀書籍「自分の親に読んでほしかった本」の要約・内容が知りたい
🍀親子関係の絆を深めたい人
🍀これから親になる人、現在子どもとの接し方に悩んでいる人
書籍「自分の親に読んでほしかった本」をご紹介します。本書にはどんな思いが込められているのでしょう?私たちが育まれた家庭環境や教育の影響は、私たちの人格や価値観を形成する大きな要素の一つです。そして、本書を通じて得られる知識は、子どもにとっても素晴らしい刺激になると思いました。この記事では、本書の魅力を紹介するとともに、親子関係を改善するヒントや実践的なコミュニケーション術についても考えていきます。
本書を手に取ることで、親子の関係をより豊かに育むきっかけが生まれるのではないでしょうか。親にとって心に響く部分や、試し読みで確認する方法についてもご紹介します。さらに、親子関係を深めるための具体的なステップや、物語を通じて子どもの感情や思いやりを育むヒントも掘り下げていきます。
それでは「自分の親に読んでほしい本」の魅力と選び方を知り、新たな親子の絆を見つける旅に出かけましょう。
試し読みできる?
Amazonからできる!
なんと153ページも試し読みができます!(25.7現在)
全354ページなので、半分近く無料で読めてしまいます。
第1章 子育ての遺産は連鎖する
子育てにおいて最も邪魔なものとは?
それは、親が子どもの頃に受けた体験とされています。
本書によると、子どもの行動にイライラしたり、強くやめてほしいと感じるのは、今目の前で起きている出来事そのものではなく、親自身の過去が刺激されているからだといいます。著者のフィリッパ・ベリーさんは、こうした無意識の反応が子育てに影響を及ぼすと指摘しています。
例えば‥
あなたが中学生の頃、親から「勉強しなさい」と何度も言われ、成績を非常に重視されていたとします。成績が悪いと叱られ、自己評価が下がったり、大きなストレスを感じていたかもしれません。
そんな経験があると、自分の子どもがゲームやスマホばかりで成績がふるわないとき、当時の感情がよみがえり、強い不安や苛立ちを感じてしまうのです。
このように、子どもの頃の苦い体験が、親としての今の感情や行動に大きな影響を与えている可能性があるかもしれません。
ですが反対に、子どもの頃の楽しかったり嬉しかった経験が、今の子育てに良い影響を与えている場合もあります。そうしたことは、むしろ大切にしていけばいいのです。
どうしたらいい?
子育てや家事、仕事に追われる毎日で、自分の行動を一つひとつ振り返るのは簡単ではありません。それでも、もし「今、子どもに強く怒っているな」と感じる瞬間があれば、その状況を一度冷静に見つめ直してみてください。目の前の子どもにとって、どんな行動や声かけが本当に必要なのかを考えてみるのです。
著者は、自分が親からされて嫌だったことを、無意識のうちに子どもに繰り返していることに気づくことが、最初の一歩だと伝えています。
親から受けた子育ての「遺産」は、良くも悪くも連鎖していくものなのだと著者は述べています。
第2章 子どもの環境を見直す
著者はこう述べています。「大事なのは家族構成ではなく、どう暮らしているか」であるということを。互いにどのような関係性や環境を築いているかが何より重要ということではないでしょうか。
子どもの自己認識や心の健康は、親や家族だけでなく、祖父母、シッターさん、親しい友人など周囲の大人との関わりによっても育まれます。
完璧な家庭は存在しない
理想的で完全な家庭を目指す必要はありません。さまざまな形の家族があっていいのです。大切なのは、子どもが安心できる場所や関わりを感じられることです。
親の関係が子どもに及ぼす影響は大きい
両親の関係がうまくいっていると、子どもは安心し幸福度も高まります。ある調査では、10代の子どもの7割が「両親の仲が良いことはとても大事」と答えています。両親の関係が不安定だと、子どもは精神的苦痛を感じやすくなります。
親自身の行動や感情を見直すことの大切さ
子どもへの対応が、自分の苦痛や不安から来ていないかを振り返り、気づくことが必要です。親自身が無力感や恐怖感に圧倒されていると、それは自然と子どもに伝わってしまいます。
第3章 感情に向きあう
人は頭で考える前に感情で感じる存在であり、特に乳幼児はほとんど感情だけで生きています。
子どもの感情に親がどう応答するかがとても重要で、愛情や共感を示して受け止めることが心の健康の土台になります。
親が穏やかで落ち着いた気持ちで子どもに向き合い共感すれば、子どもも安心感や満たされた気持ちを学びます。
つまり、親自身が自分の感情を整え、健全に付き合う姿勢を持つことが、子どもにとって何より大切だと著者は述べています。
子どもの感情を無視した結果
この章には、母アニスと父ジョン、子のルーカスが登場します。
ルーカスは親から愛情を注がれていましたが、両親が仕事で忙しく、頻繁に他人に預けられていました。親は「子どものために働いている」と信じていましたが、ルーカスの孤独感は募っていきました。周りに大人がいて「十分幸せだろう」と思い込まれ、ルーカスも悲しみを両親に伝えることもできず、次第に気持ちを隠すようになり心がすり減っていきました。
両親が孤独に気づけないまま、10歳のルーカスは高層階からの飛び降り未遂を起こしました。
感情を受け止められずにいると、子どもは「自分は大事にされていない」と深い孤立感を抱いてしまいます。
ここから何を伝えたいのか
問題だったのは、両親が共働きだったことではなく、ルーカスが深い孤独を感じていたことでした。
両親が「感情の受け皿になる」ことをおろそかにした結果、息子が命を落としかねない出来事が起きてしまったのです。こうした命に関わる事態は稀ではありますが、「あなたの感情を真剣に受け止めているよ」と、子どもに毎日伝えることが大切です。
第4章 親になるための土台をつくる──妊娠と出産
親になる最初のできごとが、第4章にあるーーなぜそんな奇妙な構成になっているかは、読めば分かるでしょう。妊娠と出産についてはどんな年齢の親子関係に対しても光を当てると著者は言います。
理想の妊娠に振り回されないこと
妊娠を告げた瞬間から周囲からアドバイスの集中砲火を受けるでしょうが、そのようなアドバイスに全て従おうと努力することは、子どもとの関係においては邪魔になってしまうことでしょう。
もうすぐ親になる人へ
今すぐにでも親になりたいか、逃げ出したいような気持ちか内観してみてください。心配事がたくさんあるのなら「それがなんなんだ」と考えるようにしましょう。
既に親となっている人へ
妊娠中に起きたことや、自分の妊娠中の態度や行動が間違っていたかもしれないと思っても、いま目の前にいる子どもについて考えるほうがよほど有益だと述べられています。
親にももちろんサポートは必要
エネルギーが枯渇したように感じたら、誰かのサポートを受けることを考えることが必要だと強調されています。子どもを支えられる親子関係を築くのが親の仕事なので、あなたの一番そばにいる親しい人に、必要な助けを説明しましょう。
ホルモンは母を別人にしてしまう
あなたらしくないことで涙が出たり、急に怒ってしまったりすることがあります。著者は、それでも「おかしくなったわけではない」と強調しています。
どこからともなく強い感情が湧いてくるように感じるかもしれませんが、それは普段の気持ちが少し大げさに表れているだけです。
感受性が高まっているこの時期は、赤ちゃんのニーズに敏感に気づき、応えられる大切な助けにもなるのです。
第5章 心の健康を育む
最近になって子どもの心の健康が注目されるようになってきました。この章では、子どもが誕生してから数年間のことを取り上げられています。
赤ちゃんとの対話、コミュニケーションについて
呼吸をあわせることも、立派なコミュニケーションの一つです。繰り返していくことで、赤ちゃんは受け入れられたように感じ、自分の願いが満たされることが当然だと思えるようになります。
あなた自身がそれを苦手とする場合
我々には、幼い時にされたことを他人に対してもする傾向があり、著者自身もそういった経験から相手に対してなにかの反応を返すコミュニケーションが苦手だったそうです。
もし自身に対話恐怖症の傾向があると感じても、自分を責めずに正面から取り組んだことを誇りに思うことが大切だと著者は述べています。
スマホ依存の影響は深刻
親のスマホ依存は、子どもを悩ませる原因になります。自分がされて嫌なことや人に対して距離を感じることは、子どもにも決してしないことです。今からでもやめて、関係を修復することができます。
遊びの「意味」
子どもは遊びの中で集中し、没頭しながら、一つのストーリーを頭の中で作り出しているといいます。作り出したストーリーには、始まり・中間・終わりがあり、その過程を何度も繰り返すことで、人生において必要な集中力や、仕事を最後まで責任をもってやり遂げる力の基礎が育まれると著者は述べています。
第6章 行動を変える──すべての行動はメッセージ
あなたは、子どもにとってはロールモデルです。今はそうでないと感じても、いずれそうなると著者は言います。あなたの良い行いは心からの行動なのか、はたまたそうではないのかを子どもはしっかりと見て、感じとっています。あなたは同じ行動を取るようにと無意識に子どもへ教えているのです。
今起きていることに集中すること
子どもがうまくできないことに親が不安を感じるとき、先々の心配をするより、まず「いま目の前のこと」に集中することが大事だと説いています。たとえ思い通りに進まなくても、代わりの方法を探したり、柔軟に考えたりすれば、必ず解決策は見つかるのです。
子どもの感情コントロールについて
子どもが問題行動を起こしたり感情的になったりするのは、大人が気づかないストレスや不安が原因の場合がよくあります。親が子どもに「どうしてこんな行動をするのか」とすぐに叱ったり制限したりする前に、まずその背景やきっかけを観察して理解することが大切だと述べています。
親の都合や焦りから「きちんとさせよう」「我慢させよう」とするのではなく、余裕をもって子どもを見守ることで、落ち着きを取り戻し、行動が改善する可能性が高まると著者は伝えています。
どうしてもグズグズとしてしまう時
親が子どもを責めるとき、よく「もう◯歳なのに」「弟(妹)はできるのに」と比較や年齢を理由にすることがありますが、それは子どもに劣等感を植えつけるだけで役に立たず、むしろ子どもの心に傷を残す可能性があると著者は警鐘を鳴らしています。比較は避けて、その子自身のペースを尊重し、気持ちに寄り添うことが大切だと述べています。
親子関係に終わりはないということ
親子関係は子どもが成長しても終わることはなく、ずっと続いていくものです。大人になった子どもにも、親が支えや安心感を与える役割は残るし、親がどう接してきたかは子どもの自己評価や人生観に影響を与えます。
親が子どもを尊重し、無条件の愛情と信頼を持ち続けることが大切で、たとえ関係が変化しても柔軟に対応する姿勢が求められるとしています。最終的に親自身も子どもも安心して向き合える関係を築くことが理想であると語られています。
最後に: 正直な感想・レビュー
子どもの頃の経験が、自分の子どもへの怒りに繋がっていることはなんとなく感じていましたが、ここまで本に核心を突かれるとは思いませんでした。前半の「指摘」とも受け取れる内容には、正直ドキドキしてしまいました‥。でも同時に、私って思っていた以上に過去にとらわれていたんだなと気づけたのは、とても大きな収穫です。それでもきっと、また3時間後には子どもたちに「コラーーー!!」と言っているのだと思いますが笑、心のどこかにこの本が残っている限り、大切な何かが私の中に根づいてくれる気がしています。
全354ページにわたる本書。もし可能であれば、著者の意図や考えをあなた自身でじっくり読み解き、しっかりと受け取るためにも、ぜひ手に取って読んでみていただけたらと思います😊(PR記事ではありません)
また次回の記事でお会いしましょう。ユイサでした。

コメント